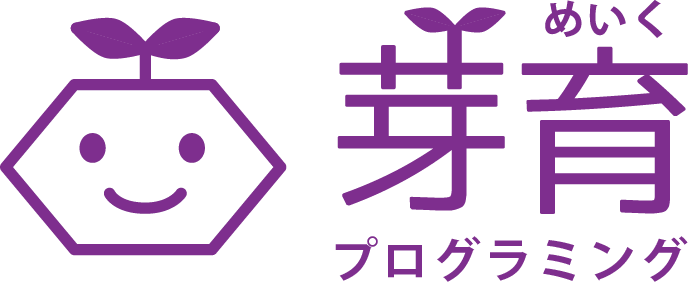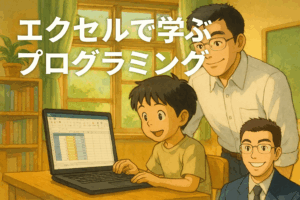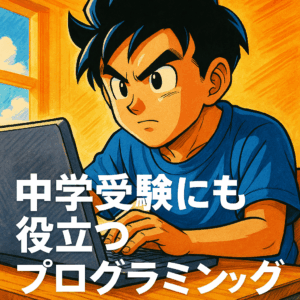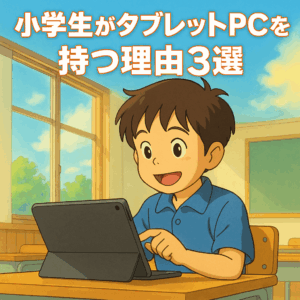ロジカルLABO芽育 姉妹校
文部科学省が定める「小学生のプログラミング教育」の内容とは?
こんにちは。キッズプログラミング教室・芽育の講師吉金です。
近年、「プログラミング教育が小学校で必修化されたって聞くけど、実際には何を学ぶの?」というご質問を多くの保護者の方からいただきます。
今回は、文部科学省が出している小学生向けプログラミング教育の指針について、わかりやすく解説いたします。
目次
◆ 小学校ではプログラミングが「教科」になるの?
まず、誤解されやすい点ですが、小学校でプログラミングが“新しい教科”として設けられているわけではありません。
2020年度からの新学習指導要領により、既存の教科の中でプログラミング的思考を育む学びが導入されたという位置づけです。
つまり、国語や算数、理科、総合学習などの中で、プログラミングの考え方を取り入れる授業が行われるようになった、ということです。
◆ 文部科学省が示す「小学生におけるプログラミング教育のねらい」
文科省の資料によると、小学校段階でのプログラミング教育には次の3つの目的があります。
- プログラミング的思考を育む
物事を順序立てて考えたり、論理的に解決策を組み立てる力を養います。 - 情報社会の仕組みの理解
コンピュータが身近にある社会で、どのように動いているのかを知ることで、テクノロジーの基礎を理解します。 - 各教科の学習を深める
例えば、算数の図形を動かしたり、理科でセンサーを使った実験をするなど、既存の学びにプログラミングを活かします。
◆ どんな授業が行われているの?
小学校では、たとえば以下のような授業事例があります:
- 国語の「説明文」において、手順を明確に書く練習としてロボットの操作手順を考える
- 算数の「図形」や「座標」の授業で、キャラクターを動かすプログラミング(スクラッチ)を活用
- 理科の実験で、センサー付きの装置を使ってデータを記録・分析(micro:bit)
これらは、「Scratch」や「micro:bit」などの教材を使って実施されることも多く、子どもたちが実際に手を動かして学べるよう工夫されています。
◆ 保護者として知っておきたいポイント
- プログラミング教育はタイピングやコード記述が中心ではない
- 「考える力」を育てる教育が目的であり、職業訓練ではない
- ご家庭でも体験できる教材やアプリが増えている
◆ まとめ:小学生のうちから“考える力”を育むきっかけに
文部科学省が推進するプログラミング教育は、「将来のIT人材を育てる」というよりも、あらゆる子どもたちに必要な“考える力”を身につける教育です。
「うちの子には難しいかも…」と思っている方も大丈夫。
遊びながら学べる教材も多数ありますし、当教室では学校の授業と連携したカリキュラムもご用意しています。
ぜひ、お子さまの“最初の一歩”を一緒に応援しましょう!