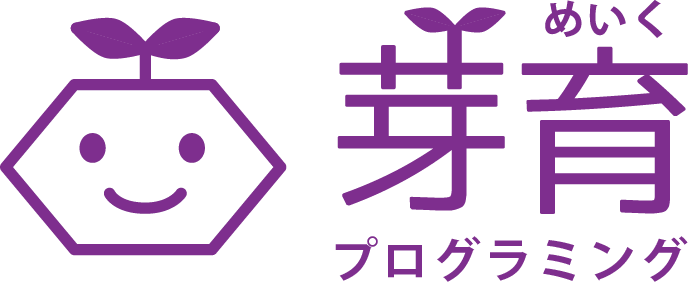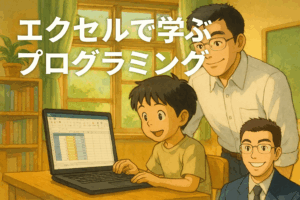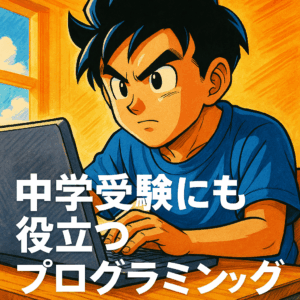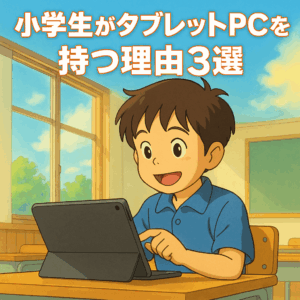ロジカルLABO芽育 姉妹校
大学入試にプログラミング?共通テストで出題された内容とは?
こんにちは。キッズプログラミング教室・芽育の講師 吉金です。
「プログラミングって難しそう…でも大学入試にも出るって本当ですか?」
最近、小学1〜3年生のお子さんを持つ保護者の方から、こんなご質問をよくいただくようになりました。
結論から言うと、すでに2025年から、大学入学共通テストに「情報Ⅰ」科目として、プログラミングに関する問題も出題されています。
今日は、低学年のお子さんをお持ちの保護者の方にもわかりやすく、どんな問題が出るのかをご紹介いたします。
◆ 2025年度から新設「情報Ⅰ」が必須に
文部科学省は、現代の情報社会に必要なリテラシーを育てるために、高校の新教科「情報Ⅰ」を設け、大学入試にも取り入れることを決めました。
この中には、プログラミングやデータ活用、ネットリテラシー、ネットの仕組みなどが含まれています。
◆ 実際に出題されるプログラミングの内容
共通テストのサンプル問題(大学入試センター公開)によると、次のような問題が出題されます。
- 「変数」や「条件分岐」「繰り返し(ループ)」の仕組みを問う
- プログラムの流れを図で示して、結果を読み取る
- 「もし〇〇なら、こう動く」などの命令を正しく理解しているか
実際にコードを書くというよりも、「論理的に考える力」や「順序立てて理解する力」が求められる内容になっています。
◆ 小学生のうちに知っておいて損はない「プログラミング的思考」
小学1〜3年生のうちは「順番に考える」「うまくいかなかったら直してみる」といった考え方を育てることが大切です。
当教室では、Scratchなど、遊びながら学べる教材を使って、お子さんの思考力・観察力・創造力を伸ばすことに力を入れています。
◆ お母さんに伝えたい、今から始める意味
今、小学1年生のお子さんが大学受験をするのは2036年前後。
その頃には、「プログラミングが当たり前にできる世代」として扱われている可能性が高いです。
でもご安心ください。
今からコツコツ遊びながら触れておくことで、「わかる・できる・楽しい!」という自信が、あとから大きな差になります。
◆ まとめ:未来の入試は「考える力」を問う時代に
大学入試共通テストの「情報Ⅰ」では、コードの正確さではなく、考える順序・仕組みの理解・データの見方などが求められます。
小学低学年のうちから、ゲームや遊びを通じてプログラミングに触れておくことで、将来の学びがスムーズになる土台ができます。
お母さんの「ちょっと気になる」が、お子さんの未来への第一歩になるかもしれません。
当教室では、低学年向けのプログラミング体験会も随時開催中です。
どうぞお気軽に、ご相談・体験にお越しください。