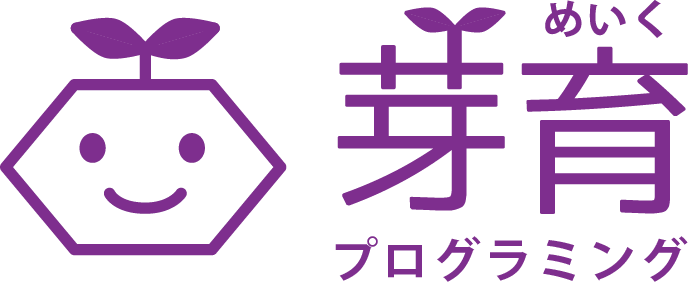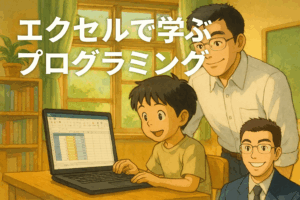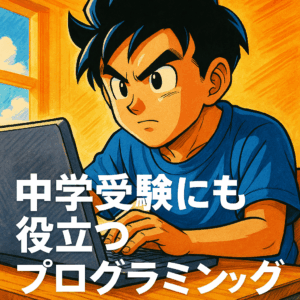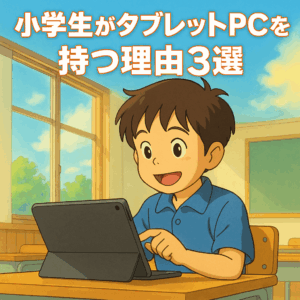ロジカルLABO芽育 姉妹校
「人生ゲーム」の中にもプログラミングが!?遊びの中にある“考える力”
こんにちは。キッズプログラミング教室・芽育の講師 吉金です。
小学生のお子さんがいるご家庭で人気の定番ボードゲームといえば「人生ゲーム」ですね。
実はこの人生ゲームの中にも、プログラミング的思考がたっぷり詰まっていることをご存知でしたか?
今回は、「遊び」の中にある「学び」として、「人生ゲームの中にあるプログラミング的な考え方」を、小学1〜3年生のお子さんをお持ちのお母さん向けにわかりやすくご紹介します。
◆ そもそも「プログラミング的思考」とは?
文部科学省が提唱する「プログラミング的思考」とは、
「目的を達成するために、順序立てて物事を考え、試行錯誤しながら最適な手順を見つける力」のことです。
これは、プログラマーに限らず、将来どんな職業に就いても役立つ“考える力”として、今とても注目されています。
◆ 人生ゲームのどこがプログラミング?
「えっ?ルーレットを回して進むだけなのに?」と思われるかもしれません。
でも実は、人生ゲームの中には、プログラミングに通じる考え方がたくさんあるのです。
- 順序立てて進む=命令の順番
ゲームはスタートからゴールまで、決められた順に進んでいきます。これはプログラムが「1行ずつ上から順に実行される」のと同じ考え方です。 - 選択による分岐=条件分岐
「職業を選ぶ」「進学する or 就職する」などの選択は、“もし〇〇なら…”という条件分岐の考え方と同じです。 - ルーレットの繰り返し=ループ
「振る→進む→イベント発生→次の人へ」という流れを、何度も繰り返してゲームを進める。これは「くりかえし(ループ)」そのものです。 - 最適な選択肢を考える=アルゴリズム
お金を増やすには?早くゴールするには?
子どもは自然とよりよい手順(=アルゴリズム)を考えて選んでいます。
◆ 小学生が遊びながら学べる最高の教材
小学校低学年の子どもたちは、遊びの中で自然に「考える力」や「ルールを守る力」を身につけていきます。
人生ゲームのようなボードゲームは、ただの遊びではなく、プログラミングの土台になる力を育てるのにぴったりなんです。
◆ 教室ではこんなふうに活かしています
当教室では、プログラミングの導入にあたって、論理パズルなどの紙教材を積極的に活用しています。
「もしこうしたら、次はどうなる?」という問いかけから、「自分で考える力」を引き出す工夫をしています。
◆ まとめ:「学び」は遊びの中にある
「プログラミング」と聞くと、パソコンの画面に向かってコードを書く姿を想像しがちですが、
小学生のうちは「考える習慣を育てる」ことが最優先です。
人生ゲームは、親子で楽しみながら「順序」「条件」「結果」を体験できる、最高の学びの入り口です。
ぜひ一度、「プログラミング的思考」を意識しながら、一緒に遊んでみてください!
当教室では、こうした身近な遊びや教材を通して、お子さま一人ひとりの思考力を伸ばすプログラムを提供しています。
ご興味がありましたら、ぜひ体験レッスンにお越しください。